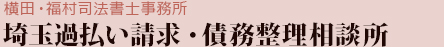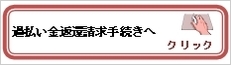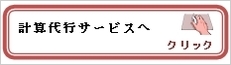埼玉県さいたま市・蕨市・川口市で、任意整理・過払い金返還請求手続き・消滅時効など借金相談をお考えの方は、債務整理を専門とする横田・福村司法書士事務所へ。
無料相談会実施中
秘密厳守・一切無料
048-863-7163
過払い金Q&A
既に完済済みの借金について過払い金返還請求するとブラックリストに掲載されるのか?
ワンポイントアドバイス
- 確実にブラックリストの掲載を避ける方法
- 借金を完済した後に債権者(消費者金融業者・クレジット・信販会社)に契約の解約手続きをすると同時に使用していたカードを返却もしくは破棄してください。
- 債権者が保管している契約書の返還(「取引終了」などと記載されているはずです。)を受けてください。
- 債権者が解約手続きを行い、信用情報機関へ「完済登録」をします。
- 信用情報機関へ完済登録されたのか債権者へ確認してください。
※業者によっては契約の終了情報の登録は毎月まとめて行ったりするなど時間がかかることもあるため、完済登録が実際にデータ上反映するのに数ヶ月かかる可能性があります。- 信用情報機関の登録抹消が確認できたら、専門家に過払い金返還請求を依頼してください。
金融庁は、「過払い金返還請求した事実」を信用情報に反映させない方針を決定しました。
過払い金返還請求をしたかどうかは個人の支払い能力とは直接関係はなく、信用情報にあたらないと判断しました。
過払い金返還請求権の消滅時効は?
原則として「最終の支払日から10年以内」であれば過払い金返還請求は可能です。返済されてから10年経過していない方は、過払い金返還請求することをおすすめします。
最高裁平成21年1月22日判決
過払い金返還請求権の消滅時効の起算点は「取引終了時」
これまで過払い金返還請求ができなくなる時効の起算点を「最後の取引の終了時」とするか「過払い金の発生時」とするかで争われておりましたが、今回の最高裁判決で「取引の終了時」とする判断がなされました。
これは、今まで一度取引があった後の再借入(「借換え」や「完済後に再貸付」)において、債務整理の結果、最初の取引で過払い金が発生している状態のまま2回目の借入をしていた状態が判明後、貸金業者と交渉すると「1回目の取引は過払い金が発生してから10年以上経過しているから時効だ。」と主張されるケースが多かったので、非常に影響の大きい判決であります。
貸金業者の主張する「過払い金が発生してから10年で時効にかかる」となると当然、過払い金の返還請求する立場としては不利でしが、「取引の終了時」だとすると過払い金返還請求が時効で消滅するケースがほとんどなくなることになります。
借換えの時点で過払い金が発生しましたが、金融会社が借換えをする前と後は別の取引であると主張しています。どうしたらいいですか?
取引の途中で借入限度額を広げて新たにお金を借りていました。(このことを「借換え」もしくは「借増し」と言います。)
この場合、法定利息での引き直し計算をすると借換えの時点で過払い金が発生しておりましたが、消費者金融会社が借換えをする「前」と「後」は別の取引であるという主張をしています。どうしたらいいですか?
一度完済してから再度借入れをしていたのですが、その場合でも過払い金返還請求はできますか?
できます。例えば、基本契約が2個あった場合でも契約番号が同じであるかどうか御確認ください。契約番号が同じである場合は、原則的に1個の連続した契約であると考えることができ一連計算できます。ただ、「完済してからの再借入」という問題は、債権者もかなり争ってくる部分ではあります。
ワンポイントアドバイス
(1)基本契約が1個である場合
- 一連計算できます。
最高裁平成19年6月7日判決
基本契約は「弁済当時、他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいる。」と判断しています。
- 基本契約が1個であれば、取引の空白期間が何年あいていようが取引は1つであるという判断ができると考えられます。
- <平成26年7月時点>途中で再契約をしていなくても空白期間が1年以上空いているだけで裁判所が分断を認めてしまう可能性もございますので、「基本契約日が記載されているATMの明細書」や「契約書」などの証拠があると、より反論がしやすい傾向にあります。
(2)「基本契約が2個以上あり、それぞれ別取引である。」と相手方が反論してきた場合
- ア)借り換えであれば、契約の切り替えにすぎず、基本契約の内容を変更しただけで1個の貸付取引であり、分断されません。
- イ)借り換え以外の場合
まず、「契約番号(管理番号)が同一であるかどうか?」をチェックします。同一であれば、基本契約は1個であることを前提に一連計算を主張して構わないと思います。
ただ、実務上、裁判所は「契約番号」だけでなく、平成20年1月18日最高裁判決を根拠に、「空白期間の長さ」や「当時の借り入れた状況」など詳細な内容を検討していくことが多いです。
取引の途中で空白期間がある場合(取引の途中で最短でも約1年6カ月の空白期間があったケース)で、契約書に自動更新条項があるだけでは一連計算ができる根拠とはならず、あくまで平成20年1月18日最高裁判決の判断基準(1.空白期間の長さ 2.空白期間時に業者から勧誘があったか 3.契約書の返還の有無 など‥)を前提に判断するべきとの判決が出ました。<平成23年7月14日判決>
貸金業者が合併した場合、過払い金返還請求するにはどうしたらいいか?また…
貸金業者が合併した場合、過払い金返還請求するにはどうしたらいいか? また、貸金業者がある会社へ債権譲渡した場合、過払い金返還請求するにはどうしたらいいか?
合併のケース
例)
- アルコ⇒シンキ(ノーローン)
- 三洋信販(ポケットバンク)⇒プロミス
- ライフ⇒アイフル
債権と債務すべてを合併先の会社が引き継ぐことになるので、合併前の会社が負担していた過払い金を支払う債務も新会社が引き継ぎます。
よって、合併先の会社に過払い金返還請求して構いません。
債権譲渡のケース
「債権譲渡前の過払い金を支払う債務は負担していない」という主張をしてくる場合もあるのですが、原則として債権譲渡先の会社に過払い金返還請求をして構いません。
通常、債権譲渡時に譲渡人と譲受人との間で「過払い金の負担」についても協議して書面を交わしているはずです。
平成23年3月22日最高裁判決
貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合において、譲渡業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは、上記合意の内容いかんによるというべきであり、それが営業譲渡の性質を有するときであっても、借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に移転すると解することはできない。
⇒これにより、債権譲渡がされても当然に契約上の地位が移転するから譲受会社が過払い金の返還義務を負う訳ではなく、譲渡契約をした際の契約内容によるということとなります。
つまり、譲渡契約に「過払い金返還義務を引き継がない」というような内容が明確に記載されていれば、譲受会社が過払い金を返還しなくてもよいという事もあり得るということになりました。
債権切替のケース
「債権切替」とは?
A社との取引において生じた借金を、B社から全額借りて返済をし、それ以降はB社と取引を継続すること
クラヴィス(クォークローン・タンポート)からプロミスへの債権切替のケースで、最高裁平成23年9月30日判決において、クラヴィス・プロミスとの取引を一連計算した上で、プロミスに過払い金返還請求ができる旨の判断が下されました。
過払い金がある時に「利息」もあわせて請求できるということですが…
過払い金がある時に「利息」もあわせて請求できるということですが、
- 利息はいつの時点で発生しているのですか?
- また、利息発生後に新たにお金を借りた場合、その利息はどのような扱いになるのでしょうか?
1.過払金利息の発生時期
平成21年9月4日最高裁判決
過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払いを継続したことにより過払金が発生した場合でも、民法704条前段所定の利息は過払金発生時から発生する。
⇒しばらく過払い利息の発生時期の問題が争点となっておりましたが、最高裁で「過払利息は過払金発生時から発生する。」と判断されましたので、これで一応決着したことになります。
2.過払い利息発生後に新たな借入を行った場合の利息の充当方法
平成25年4月11日最高裁判決
継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含む場合には、特段の事情がない限り、まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し、次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきである。
⇒要するに、「過払い元金」と「その元金に付く過払い利息(5%)」が発生した状態から新たにお金を借りていた場合、原則として、
まず
- 「過払い利息」を借金額に充当させ、
次に- 「過払い元金」を借金額に充当させて利息引き直し計算をしてくださいということです。
一部の業者で利息の充当方法について争ってくるケースがございましたが、これで一応決着したことになります。
もっと詳しく知りたい方は
当事務所で御相談があった債務整理(「任意整理手続」と「過払い金返還請求手続」中心)に関する問題点を「債務整理Q&A」に記載しております。
お問合せはこちら
メールでの御相談であれば「原則1日」で返答致します。お電話での御相談も承ります。

お気軽にお問合せください
- 借金の返済を見直したい
- 過払い金になっている可能性があるのか?
- 依頼すると、どの位費用がかかってしまうのか?
簡単な御質問でも結構ですので、どうぞお気軽にお問合せください。
秘密厳守・相談料は一切無料です。
借金(債務整理)及び過払い金返還手続きの御相談をご希望の方へ
- 「借入先」
- 「各業者の借金額」
- 「取引年数」
の3点を教えていただけるとより具体的なお話しができます。お手元に契約書やATM明細書などが無くても、御自身の御記憶をたどった大体の取引年数などで構いません。
お客様の声
借金がなくなりました

20年以上も前から消費者金融会社などで借金をしておりました。
返済するのに苦労しておりましたが、満額に近い過払い金を回収していただいたおかげで他の借金も返済でき、全ての借金がなくなりました。
こんなに精神的に楽になるとは思いませんでした!!とても感謝しております。
1ヶ月で過払い金を回収

信販会社から「父親の借金を返済してください」との請求書が届き大変不安でしたが、丁寧に債務整理手続の説明をしていただき安心しました。
当初の依頼から1ヶ月半で、過払い金の回収までやっていただきました。ありがとうございました。
ご連絡先はこちら
福村司法書士事務所(旧横田・福村司法書士事務所)
メールでのお問合せは24時間受付けています。
受付時間
9:00~18:00(土日祝除く)
※事前にご連絡いただければ土日祝、時間外の対応も可能
業務エリア
さいたま市全域・川口市・
蕨市・戸田市 ほか
※東京・栃木・群馬・茨城・千葉など他県の御相談者も対応中です。
事務所紹介はこちら